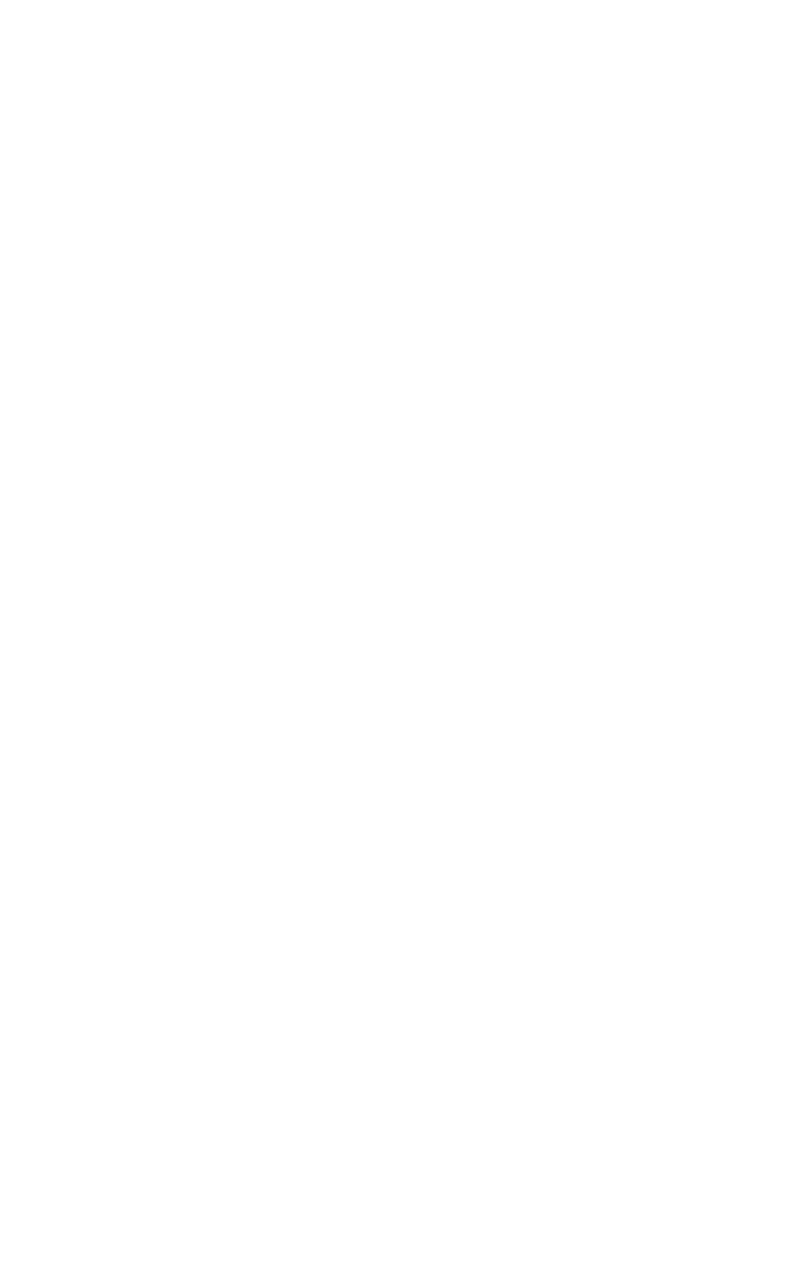
コメント
彼らは彼らなりに真剣にこの国のことを考えていたと思う。
だが行き過ぎた行動のために新左翼党派は壊滅することになった。
他にやりようがなかったのか。私のなかには残念な気持ちがある。
だが行き過ぎた行動のために新左翼党派は壊滅することになった。
他にやりようがなかったのか。私のなかには残念な気持ちがある。
田原総一朗(ジャーナリスト)
吉永小百合が 3年前まで歩いていた文学部キャンパス。
そこでひとりの大学生が殴り殺された。
殺したのは“革マル派”だった。
その後激しくなっていった内ゲバで 100人以上が命を失った。
殺すことで何かが解決したのだろうか。
そこでひとりの大学生が殴り殺された。
殺したのは“革マル派”だった。
その後激しくなっていった内ゲバで 100人以上が命を失った。
殺すことで何かが解決したのだろうか。
久米宏(フリーアナウンサー)
証言者パート、劇作パート、メイキング・パートが相乗的にかみ合って、起きていたことをヒリヒリと浮かび上がらせていた。時代の狂気のせいにしてはならない。今につながるテーマだ。
金平茂紀(ジャーナリスト)
現状の社会を批判し、夢や理想を語るからこそ、人びとの共感を得てきた〈革命〉の思想。いつしか、それは嘘と欺瞞に満ち、人びとの希望を打ち砕くような思想と実践に成り果てて、現在に至る――日本でも、世界でも。その腐臭に満ちた事態をもたらした根拠に迫らなければならぬ、この映画のように。〈革命〉に、本来の、真の息吹を吹き込むために。
太田昌国(民族問題研究)
日本でも本気出せば、ここまでできるという証左である。音楽もすばらしい。最初、ドラマ仕立てのシーンが出てきて、「あれ、また嘘くさい再現ドラマかよ」と思ったが、劇パートの役のオーディションや、そこでの学生と鴻上尚史さんとの対話など、背景をばらすことで、時代を今につなげることができた。革マル派の恐怖暴力支配に立ち上がった学生たち。本も良かったが、映画の方が視覚に訴えるものがあるのか、ずっとわかりやすい。同時代のワセダに生きた私が長い間待ち望んでいた映画。できるだけ多くの人に見てほしい。
森まゆみ(作家)
1980年の春に早稲田大学第一文学部に入学した一人として、戸山キャンパスの構内でまず目にしたのは教室や廊下や階段のあちこちが破壊された不穏な風景、何かが終わったまま投げ出された風景だった。バブルに向かう賑やかな世相の中で、そうした傷の来歴をもはや顧みようとはせず、私たちはシラケ世代と呼ばれた。いま、同世代の代島監督はシラケることなくあの時代を追及している。本作を観て、記憶の喉に刺さった小骨のままだった不穏な風景ともう一度対峙することになった。同時に、あのころ早大演劇研究会から出現し、80年代の演劇界を牽引した「第三舞台」の主宰だった鴻上尚史が本作で再現ドラマ部分を重厚に演出しているのも興味深い。公演を夢中で追いかけた「第三舞台」の軽やかな笑いに満ちた華やかなステージの記憶はいまなお鮮やかだが、本作を傍らに置いてみると、新たな意味が生じてくるかもしれない。
石坂健治(東京国際映画祭シニア・プログラマー/日本映画大学教授)
「浅間山荘」はしばしば日本の政治シーズンの血なまぐさい結末の象徴として立つが、その壮観さはなぜか内ゲバという衝撃的に広がった慣行を吸収し(そして隠蔽)してしまう。『ゲバルトの杜』では、代島治彦──私たちの時代の情熱的な年代記者が、一件の拷問と殺人事件に圧倒的な明るい光を当て、その全体的な現象とその不気味な心理を照らし出す。
マーク・ノーネス(映画研究家/ミシガン大学教授)
見始めて数分で凄惨なリンチシーンが始まり、息苦しくなった。このあと川口君がどうなるか知っているだけに余計に切ない。同じ年ごろの子供を持つ親として、これを見通すのはしんどいなと思っていると、場面は急に現代の若者がキャストとして再現ドラマを演じるメイキングシーンに転じる。
このように本作『ゲバルトの杜~』は、当時の関係者が語るインタビューを中心としたドキュメンタリー部分と、現代の若者が演じる再現ドラマ、そして映画制作の舞台裏ともいえるメイキングシーンの、三つの物語を行き来する。この転調の仕方、構成の妙が、観客を飽きさせず、映画から最後まで逃げさせない仕掛けとなっている。樋田毅さんの原作の力強さに加え、映画製作人のこうした技術的水準の高さが見ごたえのある作品にしているのだ。
映画は川口君事件に限らず、新左翼の内ゲバ事件を広範に扱っている。自らの正義を押し付け、平気で人の命を奪う。それは革マル派や中核派だけでなく今も続く。ロシアでウクライナでパレスチナでイスラエルで。舞台は1970年代の学生運動だが、根底にある映画人の問題意識は現在も照射している。
このように本作『ゲバルトの杜~』は、当時の関係者が語るインタビューを中心としたドキュメンタリー部分と、現代の若者が演じる再現ドラマ、そして映画制作の舞台裏ともいえるメイキングシーンの、三つの物語を行き来する。この転調の仕方、構成の妙が、観客を飽きさせず、映画から最後まで逃げさせない仕掛けとなっている。樋田毅さんの原作の力強さに加え、映画製作人のこうした技術的水準の高さが見ごたえのある作品にしているのだ。
映画は川口君事件に限らず、新左翼の内ゲバ事件を広範に扱っている。自らの正義を押し付け、平気で人の命を奪う。それは革マル派や中核派だけでなく今も続く。ロシアでウクライナでパレスチナでイスラエルで。舞台は1970年代の学生運動だが、根底にある映画人の問題意識は現在も照射している。
大鹿靖明(ジャーナリスト・ノンフィクション作家)
代島監督はこれまでの作品でも「大義のために友を亡くした人」に当時を振り返らせ、また当時の運動について語らせている。関係を築き、文脈を与え、その姿をアーカイブとして残したことの価値に留まらず、今作では更に斬新な方法で若者へのバトンを提示した。
知ることにより得た想像力は、どのように還元されるべきなのか。いずれにせよわたしは川口君ではなく、またリンチをした学生でもない。しかし、まさに今その隣にいるのである。
知ることにより得た想像力は、どのように還元されるべきなのか。いずれにせよわたしは川口君ではなく、またリンチをした学生でもない。しかし、まさに今その隣にいるのである。
渡邉知樹(絵本作家)
革命のために尊厳ある生命を犠牲にした
私たちの時代の闘い方の欠陥が描かれている。